自給自足を実践する、知らない土地から来た旅人との出会いが新しい可能性を生み出してきました。今回の主人公・ケンちゃんは、屋久島で自然ガイドの仕事をしながら、さらにエコロジーの実践に興味を持っている青年です。
ケンちゃんは、40日間にも及ぶ遍路の旅の途中に立ち寄ることを楽しみにしていました。そして、ここで出会った井戸作りの仕事は、彼にとって「貴重な体験」となったのです。
従来のコンクリート製井筒の上に、地元の石や河原の丸石を使って石垣を積み上げていく作業。重機を使いつつも、二人のバランスの取れた手作業が印象的でした。ケンちゃんは、将来屋久島でエコビレッジを構想しているだけに、この経験は大きな意味を持っていたのでしょう。
単なる井戸作りを超えて、自然と調和する生活の知恵が随所に見られました。粘土による雨水の遮断、小屋とツルベの設置など、一見コンクリートだけでは実現できない工夫が凝らされていました。
このような出会いと協働は、「Big Familyプロジェクト」の精神そのものを体現するものです。知らない人とつながり、新しい発見と学びを得ること。それが自給自足のコミュニティにとって最も価値ある財産なのかもしれません。
ここの暮らしは、単なる生活スタイルではなく、人と自然、そして地域をつなぐ豊かな営みなのです。ここに訪れる旅人たちとの出会いは、この暮らしの魅力を引き出し、更なる発展につながっているのです。
エコロジーに憧れる人との出会い
屋久島はその豊かな自然から、多くのエコロジー志向の人々を惹きつけてきました。今回廃材天国に訪れたケンちゃんもその一人です。彼は屋久島でエコツアーのガイドを務める「森の旅人」として知られ、縄文杉などの大自然を案内しています。しかし、それだけではなく、さらなるエコロジーの実践に夢を抱いていたのです。
そんなケンちゃんが、遍路の途中で立ち寄った、新たな可能性を見出したのは注目に値します。井戸作りを通して、自然素材と廃材を組み合わせる知恵を学び、将来の「アート村」構想につなげようとしていたのです。まさに、お互いの探求心が交わり、新しい何かが生まれようとしているのが感じ取れます。
自然と調和する生活の知恵
この井戸作りは、単なる土木作業以上の意味を持っていました。既存のコンクリート製井筒の上に、地元の石や河原の丸石を使って石垣を積み上げていく作業は、自然と調和する生活の知恵が詰まっているのです。
例えば、雨水の侵入を防ぐため、井戸の周りに粘土を埋める工夫。また、完成後には小さな小屋とツルベを設置する計画も。これらはまさに、自然とともに生きるための知恵が発揮されているといえるでしょう。
重機を使いつつも、バールでの微調整など、二人の息の合った作業ぶりも印象的でした。まさに、自然と調和しながら、必要最小限の道具を使いこなす、そんな姿勢が見えてきます。

人と自然、地域をつなぐ営み
このように、出会いと協働は、単なる生活スタイルを超えた意味を持っているのです。知らない土地から来た旅人との協力は、新たな可能性と学びをもたらします。そして、それはまた、自給自足のコミュニティにとって最も価値ある財産にもなるのではないでしょうか。
人と自然、そして地域をつなぐ。そんな暮らしは、単なる生活の工夫ではなく、より深い営みなのです。エコロジーに憧れる人たちが集い、お互いに刺激し合う。そこには、未来につながる大きな可能性が秘められているのかもしれません。
屋久島の自然を熟知するエコツアーガイド、ケンちゃんの旅は単なる遍路の道のりではなかった。「森の旅人」という屋号を持つ彼は、縄文杉が広がる屋久島の深い森で、自然と人間の共生を日々模索してきた青年である。40日間の遍路の旅の中で、彼が出会ったのは、自給自足の生活を実践する驚くべき場所だった。ここは、廃材を活用し、エネルギーから食料まで、すべてを自らの手で賄う独創的な生活空間。ケンちゃんの好奇心は、この場所が提示する新たな生活様式に、深く揺さぶられることになる。

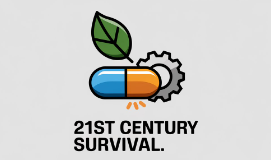


コメント