現代社会から少し離れた場所で、自然と共生する生活を実践する仲間たちが集まった。彼らの目的は、単なる趣味や好奇心ではなく、持続可能な暮らしを追求することだった。今回のワークショップは、伝統的な技術と創造性を融合させた窯づくりが中心テーマ。参加者は岡山、大阪、淡路島、そして地元の香川から集まり、年齢も20代から60代まで幅広い。彼らの共通点は、自宅でピザを焼きたいという熱い想いだった。
作業は地ならしから始まった。手動の丸太ランマで土地を均し、石を慎重に敷いていく。参加者たちは互いに協力し、チェーンソーやインパクトドライバーを使いこなしながら、丸太を切り、組み立てていく。特徴的なのは、二室構造の窯design。上下に部屋を設け、長い耐火煉瓦を使用することで、長時間の連続燃焼が可能になる。上の部屋でピザやパンを焼き、下の部屋からも火を起こせる、まさに工夫の塊だ。
作業の合間には、参加者自慢の野菜や天然酵母パン、お米などを持ち寄り、交流を深める。昼食は玄米パエリア、夜は新鮮な魚と野菜を使った料理で舌鼓を打つ。この日の最大の学びは、単なる技術の伝承だけではない。互いに助け合い、分かち合う関係性こそが、真の豊かさであることを参加者全員が実感した。貨幣を介さない、文化的な繋がりこそが、彼らが目指す生活の本質だったのだ。
自然と調和した暮らしを実践する仲間たちが集まった。彼らの目的は、単なる趣味や好奇心ではなく、持続可能な暮らしを追求することにあった。この日のワークショップは、伝統的な技術と創造性を融合させた窯づくりが中心テーマとなった。参加者は岡山、大阪、淡路島、そして地元の香川から集まり、年齢も20代から60代まで幅広い。しかし、彼らの共通点は、自宅でピザを焼きたいという熱い想いだった。
窯づくりの工程は地ならしから始まった。参加者たちは手動の丸太ランマを使って土地を均し、石を慎重に敷いていく。その後、チェーンソーやインパクトドライバーを使いこなしながら、丸太を切り、組み立てていった。特に注目されたのが、上下に2室を設けた二室構造の窯設計だ。長い耐火煉瓦を使用することで、長時間の連続燃焼が可能になる。上の部屋でピザやパンを焼き、下の部屋からも火を起こせる、まさに機能性と創造性が融合した作品といえるだろう。

持続可能な暮らし!5つの窯づくり体験で学ぶ自給自足のヒント
自給自足ワークショップの魅力とは?
• 20代から60代まで幅広い年齢層が参加
• 持続可能な生活を追求する仲間との出会い
• 実践的な技術と知識を学べる貴重な機会
窯づくりの奥深い技術と工夫
自給自足の生活において、窯づくりは単なる建設作業以上の意味を持つ。伝統的な技術と現代的な創造性を融合させた窯は、参加者たちの知恵と協力の結晶だ。二室構造という独自の設計により、長時間の連続燃焼が可能となり、効率的な調理環境を実現する。
仲間と共に紡ぐ新しいライフスタイル
この日のワークショップは、技術の伝承以上の意味を持っていた。参加者たちは互いに助け合い、分かち合う関係性の中で、真の豊かさを実感していく。貨幣を介さない文化的な繋がりが、彼らの目指す生活の本質なのだ。単なる消費者から生産者へと意識を転換する、新しいコミュニティの形が here に芽生えていた。
学びと成長の過程
窯づくりを通じて、参加者たちは自然との調和、持続可能な生活の知恵を学んでいく。チェーンソーやインパクトドライバーを使いこなしながら、協力して一つの作品を作り上げる喜びは、技術の習得以上の深い意味を持つ。
自給自足への第一歩
このワークショップは、持続可能な暮らしへの第一歩を踏み出す、貴重な機会となった。参加者たちは、単なる技術の習得だけでなく、新しいライフスタイルの可能性を体感したのである。
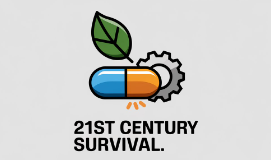


コメント